『伊豆ぐり茶紀行』
今年の春、仲のいい女友達と伊豆半島を旅行した。
「このお茶、美味しいわ。何というお茶かしら」。彼女は残りのお茶をごくりと飲んだ。白い首筋が軽く動いた。お膳の用意をしていた仲居さんが、「お客様、お出ししていますお茶は、ぐり茶と申します。伊豆半島でしか生産されてないお茶でございます」。
僕も一口飲んで、口の中で転がしてみた。「美味しいお茶ですね。初めて出会った味です」と僕は仲居さんの手の動きを見ながら言った。まろやかな甘いお茶だった。
「ぐり茶は何処で買えますか」と彼女が小首を傾げて聞くと、「お客様、私どもの旅館でもお分けすることができますよ」とにっこりと笑って答えた。
彼女は迷うことなく、「私の家は四人家族ですから、そうね、とりあえず500グラム頂こうかしら」と仲居さんに注文した。仲居さんは頭を深く下げて、ありがとうございます。後ほどお持ちいたしますと返事した。
旅館の海鮮料理はとてもおいしかった。鯛のお刺身が特に美味しかった。
露天風呂で一時間ほどゆっくりして部屋に戻ると、彼女はぐり茶を注いでくれた。部屋の布団は別々に敷かれていた。
「電気消していいですか」と彼女は言った。
遠くのいさり火が一層鮮やかに見える。彼女を抱き寄せると、心臓の音が伝わる。深い口づけをすると、お湯の香りとともに彼女の息からはぐり茶の匂いがした。
『東京から見た夢』
今年もまた、あの季節がやってきた。
私は九州は福岡、緑茶の名産地として知られる八女の出身だ。
実家が茶葉栽培を営んでおり、
毎年夏になると茶摘みを手伝わされていた。
両親と2人の兄と、5人で力を合わせて働いたあとに飲む
新鮮な茶葉で淹れた緑茶は格別においしかった。
幼い頃からこの季節はそうやって育ってきたが、
18歳、大学に進学するのと同時に私は上京した。
上京して初めての夏、私は生活費の援助があまり無かったので
アルバイトを掛け持ちして、毎日バイト三昧の日々を送っていた。
バイト先のカフェで出逢った1つ年上の彼氏もでき、
田舎育ちの田舎者だった私も都会の生活に慣れていった頃だった。
この夏は実家に帰省せず、生まれて初めて
茶摘みをしない夏を過ごしていた。
私は寂しさを感じながらも、毎日の忙しさで
あの緑茶の味を忘れ始めていた。
2年目、3年目の夏も相変わらずバイトに恋に忙しく、
正月はさすがに帰省していたが、夏に帰省することはなかった。
4年目の夏。
就職活動も一段落し、今までバイトをしてきて貯金も少しでき
余裕が出てきたので、上京して初めて夏に実家に帰った。
その頃の私は、1年の時から付き合っていた彼氏との恋が終わり、
少し気分が落ち込んでいた。
実家に着くと、正月には匂わなかった、
みずみずしいあの香りが辺り一面に広がっていた。
その香りが身体を通り抜けた瞬間、私はなぜか涙が溢れていた。
この懐かしくて温かい香りに包まれて、とても安心した。
さっそく実家の手伝いをしたが、久しぶりだったので
どこかぎこちなかったが、何とか無事に作業を終えることが出来た。
できたての緑茶を飲みながら、私はとても心地の良い眠気に誘われて
いつの間にか着替えもしないまま、居間で寝てしまっていた。
その時に見た夢は、ハッキリとは覚えてないが、
とても温かな夢だった気がする。
就職先も東京で、しばらくは都会暮らしが続くが、
毎年夏には帰ってこよう、と改めて思った夏だった。
おんなの一服
会社をリストラされてからこのかた、奈緒は疲れていた。毎日再就職のために歩き回り、
今日も手ごたえのない面接を終え、疲れた脚を引きずって歩いていた。
ふと前を見ると新しく出来たお店があった。甘味処と看板に書いてある。
ちょっとレトロな和風の佇まいに心惹かれて、奈緒はその店で休憩することにした。
店へ入ると着物を着た店員さんが立っていた。奥の席に案内されついて行くと、
窓から中庭が見えてなんだかとても落ち着く。
あんみつやわらび餅などもあったが奈緒は緑茶のセットを注文した。
しばらくして店員さんがお盆に載せた緑茶と和菓子を持ってきた。
淹れたばかりのお茶の香りが心地よい。思わずほっとする。
昔文化祭で茶道部の友達に立ててもらった抹茶を思い出す。
あの頃の元気な自分が取り戻せたら良いのに…と、奈緒は半ば諦めながら思う。
しかし、甘い和菓子と緑茶の心地よい香りのお陰なのだろうか。
少し元気になっている自分に奈緒は気が付いた。
(こんなことで元気が出るなら茶道でも始めようかな)
などと、考えをめぐらせながら余韻を楽しんでいる。
お会計を済ませ、店を出るとなんだかさっきまでとは違う空に見える。
「よーし、がんばるぞー!」
奈緒は力強く歩き始めた。
『その日の湯のみ茶碗』
「僕にお嬢さんを下さい。絶対幸せにします」
その言葉を聞いて、真奈美は面食らった。
テーブルの向こうで、佐伯が深々と頭を下げている。彼の隣で、娘の葉子が祈るような表情を浮かべていた。
佐伯は二十五歳の若者だ。彼の父親は、地元で有名な不動産会社を経営している。
そして葉子は、彼と同い年である。二人は、もう二年ほど交際していた。それで今日、結婚の申し込みをしに来たというわけだ。
「……ちょっと待って下さいね」
真奈美は大きく息をつき、椅子から立った。そのままキッチンへ移動する。
二人の不安げな視線が追いかけてくるのを感じた。
真奈美は湯呑み茶碗を三つ準備した。急須に緑茶の茶葉を入れる。
ポットのお湯を湯冷ましにたっぷりと注ぎ、じっと待った。
佐伯と葉子との結婚を許していいのかどうか。真奈美は一心に考える。
真奈美は夫に早く先立たれ、女手一つで葉子を育ててきた。
自分がさまざまな苦労をしたからこそ、葉子には豊かな暮らしをさせたい。その点、
佐伯は経済的に恵まれているから、心配はなさそうだ。
ただ、彼はおぼっちゃん育ちの一面がある。苦労を知らない分、
頼りなさも見え隠れする。そういう男性に、葉子を託していいのだろうか。
そろそろ、お湯が適温まで冷めた。真奈美は急須にお湯を注いで蓋をした。
茶葉のうまみを引き出すため、一分ほど間を置く。
そう、いつだったか、街で佐伯と葉子を偶然見かけたことがある。
二人はとても楽しそうに、何やら話しながら通り過ぎていった。
葉子の笑顔は、親に見せるものとは一味も二味も
違っていたような気がする。
佐伯には、葉子を幸せにする力があるのかも知れない。
そう感じた時、真奈美の心は決まった。
急須から、湯呑み茶碗にお茶を注ぎ分ける。最後の一滴まで丁寧に注ぐ。
お茶の濃い緑色と深い芳香が、真奈美の心を落ち着かせた。
結婚おめでとう、と口の中で言う。真奈美は湯飲み茶碗をお盆に載せ、
二人が待つ居間へと引き返した。
『茶柱妖精奇譚』
茶どころとして有名な日本のある村では、古来より云い伝えがあった。それは茶柱が3本同時に立つと茶の妖精が現れて願いを叶えてくれるというものだった。人々はこぞって茶を飲み、茶を入れるたびになんとか茶柱が立たないかと躍起になっていた。
ある時小さな女の子が、母親が買い物で留守にしている間、一人で留守番をしていた。喉が乾いたので、何気なく茶を注いだところ、見事に茶柱が立った。しかも3本立っている。彼女はまだ幼すぎて、大人たちの信じている伝説など知る由もなかった。
女の子が茶を飲んでいると、部屋の片隅から湯気が立ちのぼった。女の子は驚き、そのつぶらな瞳を見開いた。湯気に続き、七色の光が輝いた。眩しくて直視できないほどだった。
やがて湯気と光がおさまると、そこには一人の若い女性が立っていた。そう、彼女こそまさしく茶の妖精だったのだ。おもむろに妖精は小さな女の子に語りかけた。「はじめまして。私はあなたの願いを叶えるためにやってきました」と。
女の子はしばらく驚いていたが、女性の穏やかで優しい物腰に安心し、打ち解けたのだった。「ねがいかー、よくわかんないけど、おちゃがすきだから、おちゃがいっぱいほしいな」 少女は屈託なく、そう言った。妖精は「かしこまりました」とだけ言って、微笑みを保ちながら静かに消えていった。女の子はたったいま起きた出来事が現実だったのか夢だったのか区別がつかなかったが、そのまま深く気にもとめず、過ごしたのだった。
それから20年が過ぎた頃、彼女は大学を出て、新種の茶を開発する研究員になっていた。やがて彼女が開発した茶は日本の飲料業界に革命をもたらしたのだった。賢明にも特許を取得していた彼女は莫大な特許料を得て、それを元手に広大な茶畑を購入した。そこでさらに改良した品種の茶を栽培し、日本はもとより、世界中に良質の茶を供給していった。彼女は富と栄誉、そして大好きな茶に囲まれて幸せな人生を送った。
彼女の成功のかげに茶の妖精の存在があったことは誰にも知られていない。
『ウサギ』
注文伝票を見て、唸り声を上げる。
今回は何のお茶を頼もうか。
お茶はいつもならほうじ茶、緑茶、ちょっと変わって日本のお茶屋でありながら作られている
紅茶を何種類か頼むことにしているが、それではいつもと同じで面白くないような。
むう、と唸って、ペンで紙をつつく。
大体にして私は別にいいのだが、それでも気にしてしまうのが、
このお茶を一緒に飲むやつが無上のお茶好きだからだ。
-まったくウサギのクセになぜ茶を好む?
そうは思うがウサギはお茶があれば、小さな丸い尻尾をひょこひょこさせて茶を飲み、
嬉しげにひげを動かす。
その様を見ていると、なんだか毎日お茶は煎れてやらねばならないような気がするし、
選ぶときにはこだわって選ばねば、という気になってしまうのだ。
直立二足で立ち、かつ歩く『ウサギ』(日本、いや地球の生き物ではない)は、
今はちょっとそこまで、といって、カナダだかアフリカだかまで行っている。
現地調査があるらしい。
ふああ、ああ。
あくびをかみ殺してもう一度ペンを取り上げる。
このクーポンつきのお茶の注文締め切りは明日までなのだ。
今日中に書いておいて、できれば明日家を出る時に送ってしまいたい。
銘柄にはうるさくないくせに、いいお茶がはいると、嬉しそうに身を乗り出して
湯気を受けるウサギを思い出し、なんだか淋しいような気持ちになって
早く帰ってこないかなと呟きながら、
団子など和菓子と良く合うと書かれた
『月のウサギ』という銘柄の欄に、ペンの色を塗りつけた。
『イギリスにて』
ヒロコは日本人だが、学生の頃からイギリスに留学し、
そのまま住み続けて既に30年が経っていた。彼女は静岡県の茶の名産地の出身だった。
家は農家で、茶を作っていたので、子供の頃から家で毎日のように茶を飲み続け、
茶の栽培の手伝いをさせられていた。
ヒロコは幼いながら、たまには他の飲み物も飲みたかったし、
茶畑での作業などせず、もっと友だちと遊びに行きたかった。茶の臭いにも
うんざりしてしまっていた。
身の回りのすべてが茶を中心とする生活で、
思春期から両親に対して反発し、親子喧嘩が絶えなかった。
その結果、ヒロコは遂に日本を飛び出すことを決意したのだった。
皮肉なことに、ヒロコの留学先であるイギリスは紅茶の文化が伝統として残っている国だった。
アフタヌーンティなどの習慣もいまだに行われている。
イギリスで一般的な紅茶は、日本の緑茶とは若干異なるものの、茶は茶だ。
当初は抵抗を感じていたヒロコであったが、つきあい上、
やむを得ず紅茶は飲むようになっていた。
あるとき、親しい友人の一人が最近流行している日本の緑茶の茶葉を手に入れてきた。
非常に高価なものらしかった。友人宅ではその茶をふるまう会が行われ、ヒロコも招かれた。
友人に促され、久々に茶というものを飲んでみた。
すると、不思議な懐かしさというものが甦ってきていた。
「認めたくはないがこのお茶は美味しい」
とヒロコは思った。
友人が取り出した茶のパッケージを見ると、それはまぎれもなく
彼女の出身地のものだった。
彼女の眼からは大粒の涙が溢れ出ていた。
家を飛び出してから30年間一度も連絡をせず、帰っていない故郷。
いてもたってもいられなくなり、
彼女は翌日日本行きの飛行機に乗っていた。
『座長と俺』
「今日も、ウケなかったな……」
座長が残念そうな顔で言った。
公演を終えた劇団の楽屋の一角、満足そうにしている劇団員の輪には加わらず、
長椅子の端で俺と座長の二人は暗い表情で煙草をふかしていた。
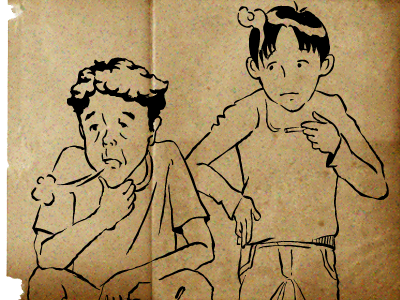
ウケなかった、というのは、
劇の中盤で座長がテーブルからお茶の入った湯飲みを足に落とし、
熱さと痛みで舞台を転げまわるというベタだがコミカルなシーンのことだ。
当然湯呑の中のお茶は冷めたもので、熱いように見せるのが
キモなのだが、半年前の公演で湯呑を客席に蹴飛ばしてしまってから
座長の演技は嘘くさくなり、
このシーンで笑いが取れなくなってしまっていた。
「お疲れしたー」
一通り騒ぎ終わって、劇団員たちが楽屋を後にし始めた。
「ちゃんと衣装、ハンガーに掛けておくんだぞ。明日も使うんだからな」
「ウッス。あ、そうそう、座長、明日はウケ取ってくださいよ?この劇場の最終公演なんですから」
「お、おう」
座長若い劇団員の軽口に、うろたえつつ返事をした。普段は劇団員を
まとめる頼れるリーダーであるだけに、今の姿は見ていて非常に痛々しい。
「こんなんで大丈夫かな……」
胸に不安を抱えながら、俺は次の日の公演を迎えた。
緞帳が開き、問題のシーンが近付くにつれて、座長の顔はひきつっていった。
声をかけても、座長は無言で頷くばかりで変わらない。今回もだめか、
と俺は半ばあきらめてしまった。
――がしゃんっ!
お茶が座長の足にかかった。
「ッ!」
座長はとっさに右足を抱えようとかがみこむ。
が、セットのテーブルのせいでそれも叶わなかった。
「あ痛っ」
客席にクスッと小さな笑いが生まれた。
そこから、座長は昨日まででは考えられないようなコミカルな演技をした。
「熱いんですか?」
「痛いんだよ!」
「痛いんですね?」
「熱いんだよ!」
「痛くて、熱いんですね? 熱くて、痛いんじゃないですね?」
「どっちでも一緒だろうが!」
お決まりの問答がスパッと決まった時、客席で笑いが爆発した。俺は
これまでになく清々しい気持ちで舞台を降りた。
劇が終わり、楽屋で全員がそろうと座長はいきなり怒鳴った。
「…誰だ!
舞台に、
熱々の お茶を、
持っていった、 奴は!」
なんと、今日の座長の演技は演技ではなかったのだ。
「えっ、知りませんけどー」
そう言いつつ、若い劇団員は笑いをこらえている。
知らなかったのは、
俺と団長だけだったようだ。
その夜の打ち上げが大いに盛り上がったのは、言うまでもない。
『恐ろしいほどに風変わりな男』
あるところに特異体質をもった男がいた。彼は一般の人々と異なり、
普通の水に対してはアレルギー症状を起こしてしまうのだ。男の家系では過去においても
同様の体質をもった祖先がいたらしく、その言い伝えにより、彼は口から飲む
一切の水分は茶として摂取していた。
飲料用だけでなく、料理をするにも、まず茶を沸かし、それを使って煮炊きしていた。
さらには手や顔を洗うときも、風呂に入る時も茶を利用していた。これは彼がまだ
赤ん坊の頃、母親が普通の水で沸かした湯につけたところ、ひどい炎症を
起こしてしまったことから、以来徹底されてきたことであった。
20歳を過ぎた頃、彼の体には変調が現れ始めた。なんと
体が消えてしまうのである。男は最初驚いていたが、やがてその現象にも慣れ、
次第に自らの意志でそれを制御できるようになった。その能力を使って、
透明な状態で街に出かけては人々を驚かせて楽しんでいた。
ある時いつものように透明茶男は街を闊歩していた。しかし人々の目には
見えない。そんなとき、民家の前で、いたずらな男の子が放った水鉄砲の水が
勢い良く体に触れ、全身に傷を負ってしまう。
どんな薬を投与しても効き目はなかったが、困り果てた医師が、濃度を極限まで高めた
茶の浴槽に体を浸したところ、短期間で効果が出て、一週間後にはほぼ完治したのだった。
この不可思議な男は果たして普通の人類なのか、はたまた、
別の惑星からやってきたエイリアンなのか、それはいまだに謎のままである。
『珈琲カップ』
私はそれまで珈琲派だった。
でも彼と一緒に住み始めて、緑茶の味が美味しいと感じるようになった。
これが2人で住むということ、2人の時間を共有するということかと改めて実感した。
最初は、昔から珈琲派だから日本茶は飲まないと言い張っていた私。
煙草に合うのは珈琲だけだということを、ポリシーのように振舞っていたのだ。
ただそれは、年上の彼に対しての、私なりの大人感を装っていたに違いない。
幼稚な感覚だと思われるだろうが、当時はほんの些細なことでも、
ポリシーを振りかざすことで安心していた。
彼はそんな私にいつも優しかった。
時が経つにつれ、いつの間にか私は珈琲カップよりも、
湯呑み茶碗を手にすることが多くなっていった。
彼がそうしろと言ったわけではない。
2人の時間は、趣向を共有するということだ。
私の、煙草と珈琲という絶対的ポリシーを、
思っていたより早く手放すことになった。
いや、
手放したというより、ただ頑なに握っていた拳を
開いただけだ。
そして、彼と、彼の好きな緑茶と、緑茶と珈琲という
新しいハーモニーを手に入れることになった。
美味しい緑茶は、煙草をより美味く感じさせた。
燻ゆる煙のなか、香ばしい緑茶を飲みながら、
彼の背中を追い、共に歩んでいく日々が続いた。
永遠に続くと信じたかった。
ある日、
ついに2人の部屋のキッチンから
湯飲み茶碗も、珈琲カップも消えた。
あれから十数年。
今の私は、やっぱり煙草には珈琲が合うと感じている。
でも緑茶と煙草も合う。
緑茶は本当に、本当に美味しいのだ。
『父の湯飲み』
「親父、親父っ!」
俺が大学2年の冬、親父が死んだ。
脳梗塞だった。
仕事もあまり上手くいっておらず、健康診断で何度も悪い値が出ていたのに、
ストレスから酒とたばこがやめられない典型的なダメ親父だった。
目つきが悪い、だとか、服装が気に入らない、などという理不尽な理由で何度も殴られた。
食後、テレビを見ているときに、馬鹿でかい湯のみで
お茶をすする音がうるさかった。
親父が死んで、俺の胸を吹き抜けたのはほんのちょっとの寂しさと、
大きな安堵感だった。
親父のいない食卓は、平和で、安らかで、
ほんの少し、静かだった。
食後、テレビを見ていると俺はふと気がついた。
茶をすする音がしない……。
家の中にぽっかりと穴があいてしまったような、
不思議な気持ちがした。時が経つにつれ、その穴は
小さくなるどころか大きくなり、ある日俺は我慢が出来なくなって
親父の湯飲みを食器棚から取り出し、
お茶を注いだ。
「あら、あなた、お父さんのを使うの?」
おふくろの手には普段俺が使っている
小ぶりの湯飲みがあったが、俺は
「ちょっと、ね」
なんて言いながら馬鹿でかい湯呑に目いっぱい口を近づけて、
綺麗な黄緑色をしたお茶をすすった。
「ずずっ……」
耳慣れた、
あまり綺麗じゃない音がした。
ふっと笑いが込み上げてきて、俺は湯呑の中を覗き込んだ。
黄緑色のお茶の水面には、最近親父によく似てきた垂れ気味の目じりと、
つんと尖った鼻が反射していた。
親父はきっと、この場にいる。
家の中の穴が、少し埋まった気がした。
